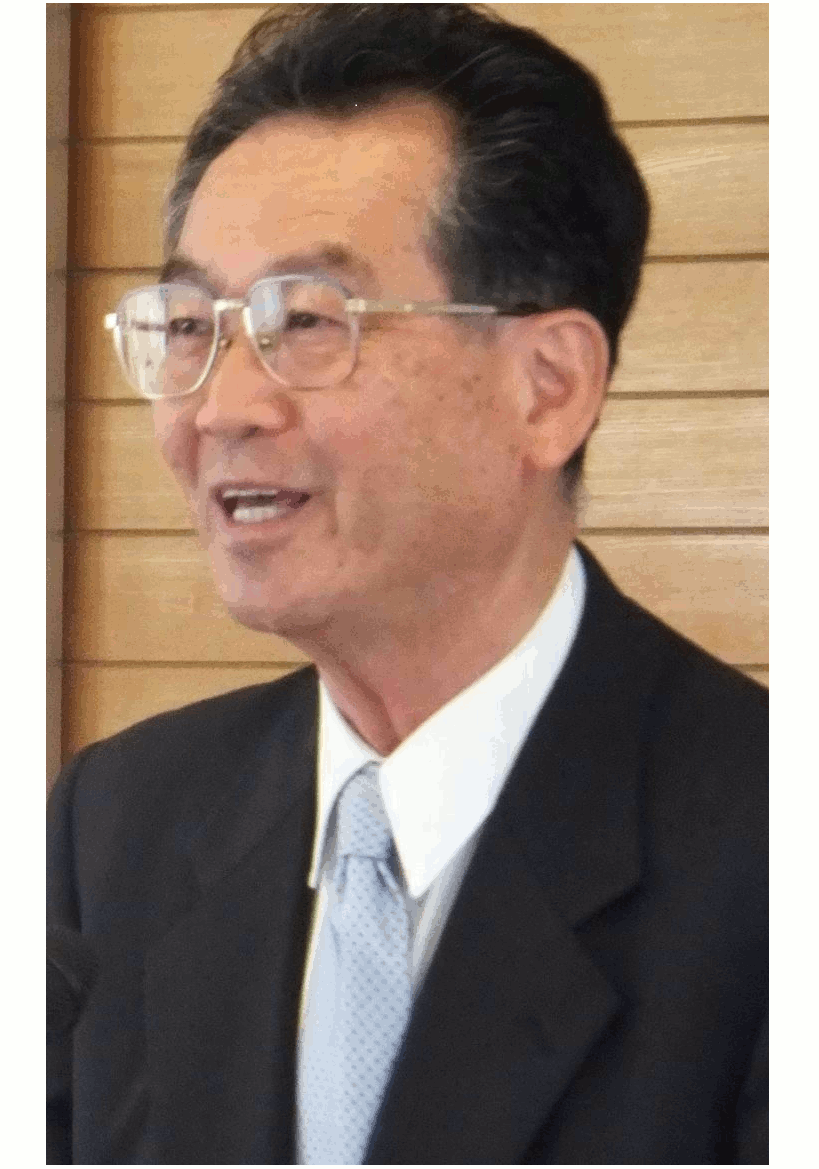|
W.M.ギャロット先生について創立記念日にお話ししましたが、それも含めてもう一度先生の事について、触れたいと思います。
私は先生からギリシャ語と新約聖書原典購読を習いました。先生は左利きでしたので、黒板には独特の書体で字を書かれました。
漢字もよく知っておられて、 ある授業時間に黒板の漢字の間違いを指摘しようとしたら、間違っていたのは私の方でした。
そしてにやりと笑って、「寺園さん、私はあなたが生まれる前か
ら日本にいますよ」と言われてしまいました。
教室は爆笑に包まれ、私は赤面してしまいました。
チャペルでは、ステージ上の椅子に長い脚を大きく組んで腰かけ、祈るときも足を組んだまま右手をつぼめて額に当て、また話し出すと大きな身振り手振り
をし壇上を行ったり来たりして、大きな声を出されました。
当時の日本ではあまり行儀がよいとは言われなかったかもしれません。先生が語られた中で今でも
覚えているのは「使命感を持った生き方をしなさい」という言葉です。
ただ動物的に本能的に生きるのではなく、人間らしく目的を持って生きなさい、という
事をしばしば話されました。
私自身は高等学校を卒業するとすぐに、牧師を目指し周囲の反対を押し切って神学部に来ただけに、何を今さら分かり切った事を
と軽い反発を覚えたものでした。
しかし先生の言葉は、非常に重いご自身の経験から生まれてきたのだということを、その後に知りました。
第二次世界大戦前、このギャロット先生は、日米関係が緊迫しすべての宣教師たちが米国へ引き上げる中、日本のことが心配で家族を帰した後、ただ一人日
本に留まられました。
戦争が勃発すると、敵国人として収容所に入れられました。収容施設は多摩川のカトリック教会で外出等は自由でしたが、食糧物資の配 給はなく、八百屋の前に落ちている野菜屑を拾って食料の足しにされていたそうです。
一人の日本人クリスチャンがこれを聞き、自分の家族の配給物資を割い て、先生の健康維持に努めたということです。
先生は1942(昭和17]年2月の最後の日米交換船で強制送還されたのでした。帰米後は主に日本人の収容キャンプ で奉仕されました。
先生はある外国伝道のための大集会に招かれ、メッセージをするようにと指名されました。
しかし講壇に上がった先生は様々な思いに一度 に襲われて、そこに立ちつくしたまま一言も言葉を発することができませんでした。
傍らにいたミッション・ボード総主事のM.T.ランキン博士が、「日本 を愛している者のみが知る心の苦しみ、愛の悩みです」と言って、先生の沈黙を取り繕ってくれました。
戦争が終わると先生は直ちに来日し、戦後の学院の 発展に寄与されたのでした。
「使命感をもった生き方をしなさい」という言葉は、何よりも先生自身の生き方でした。
だから私達にも伝わってきます。
生き甲斐とか生きる意味などの喪 失が多く語られる今の時代、使命感を持ち頭を上げ胸を張って、日々を過ごしたいと思います。(2004年6月)
(”西南の風” 寺園喜基)
|